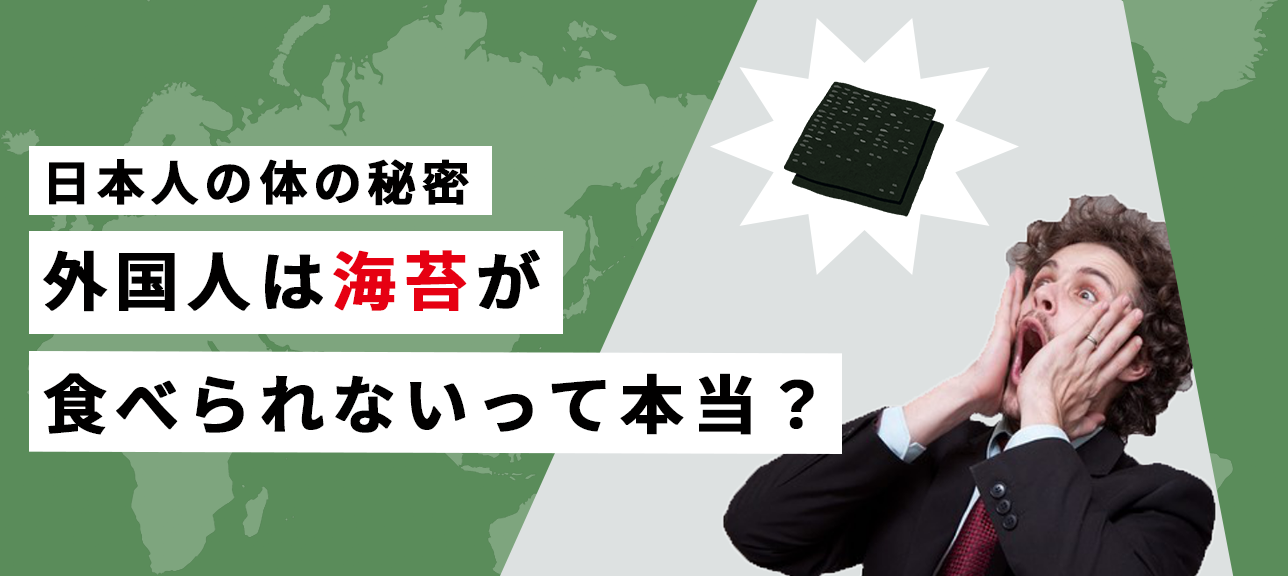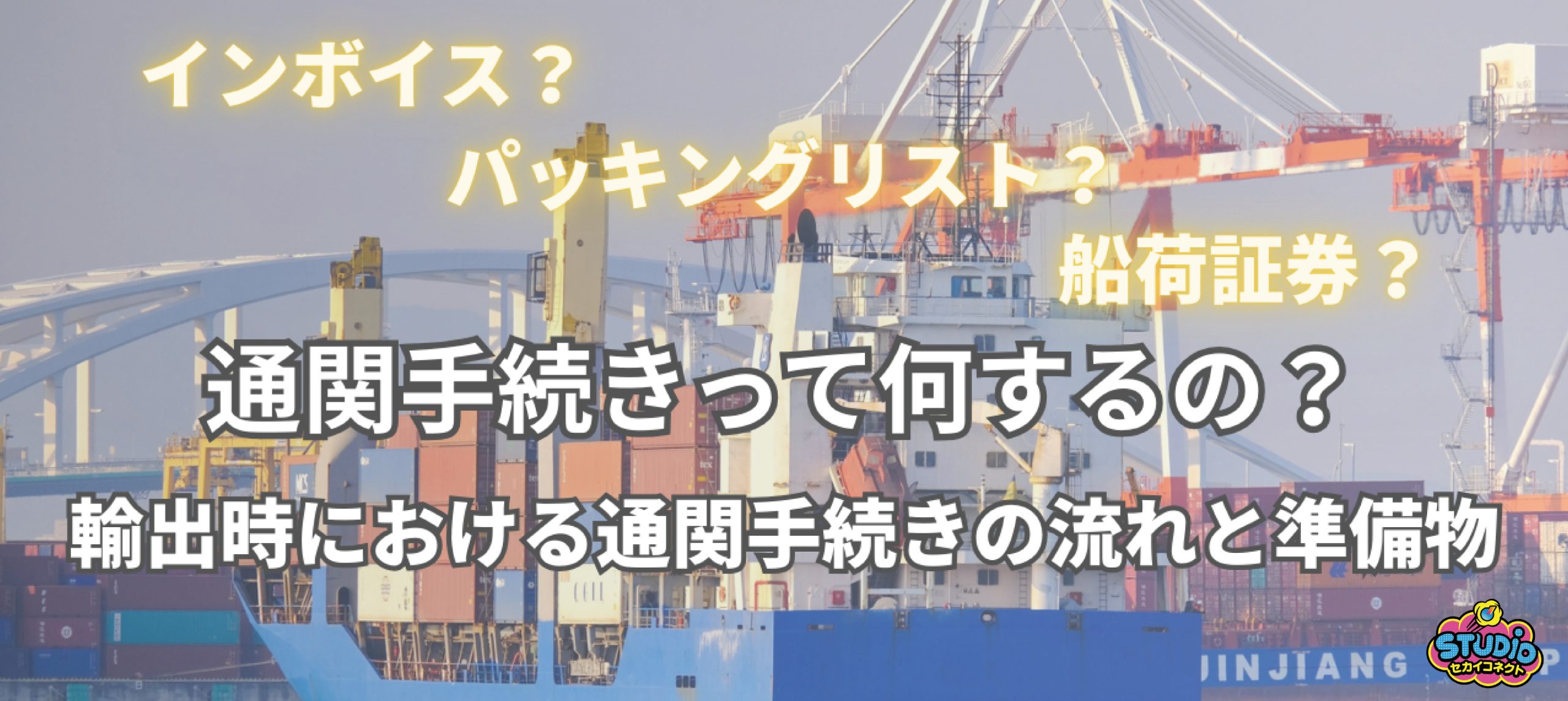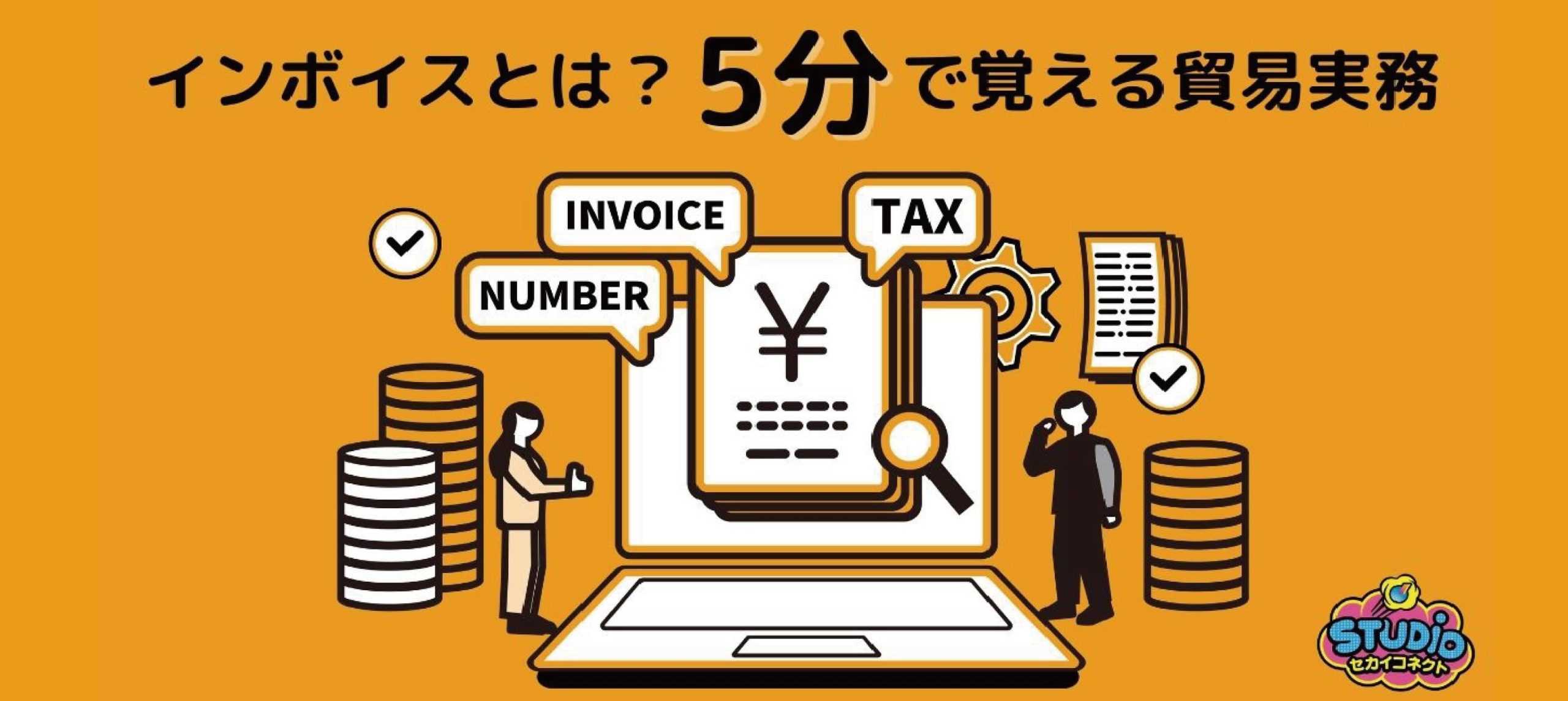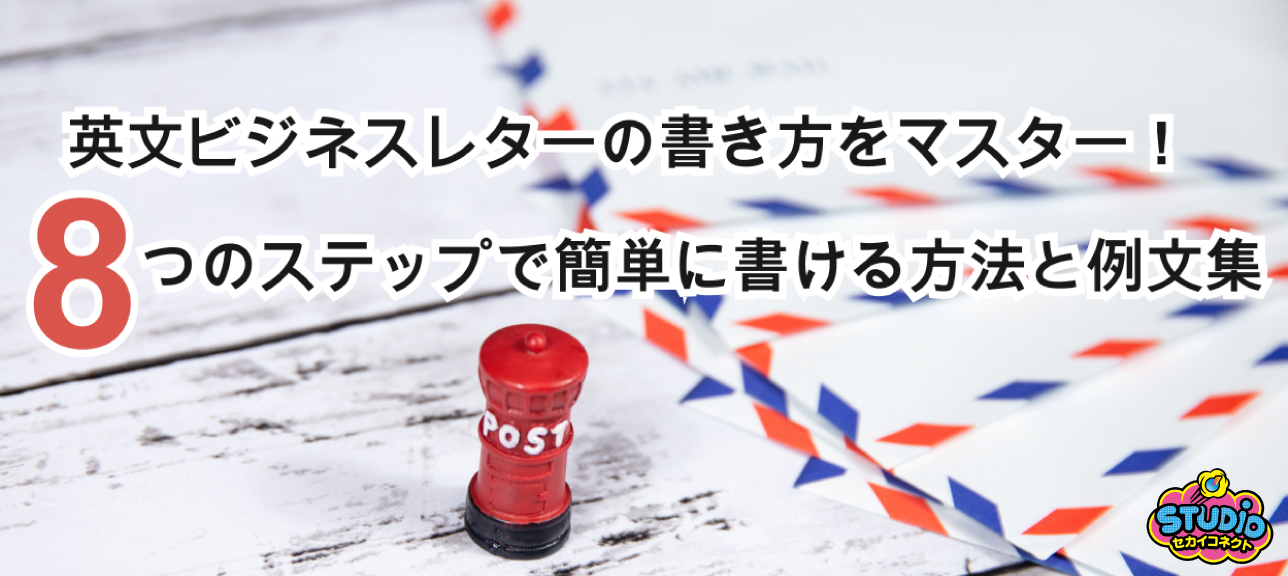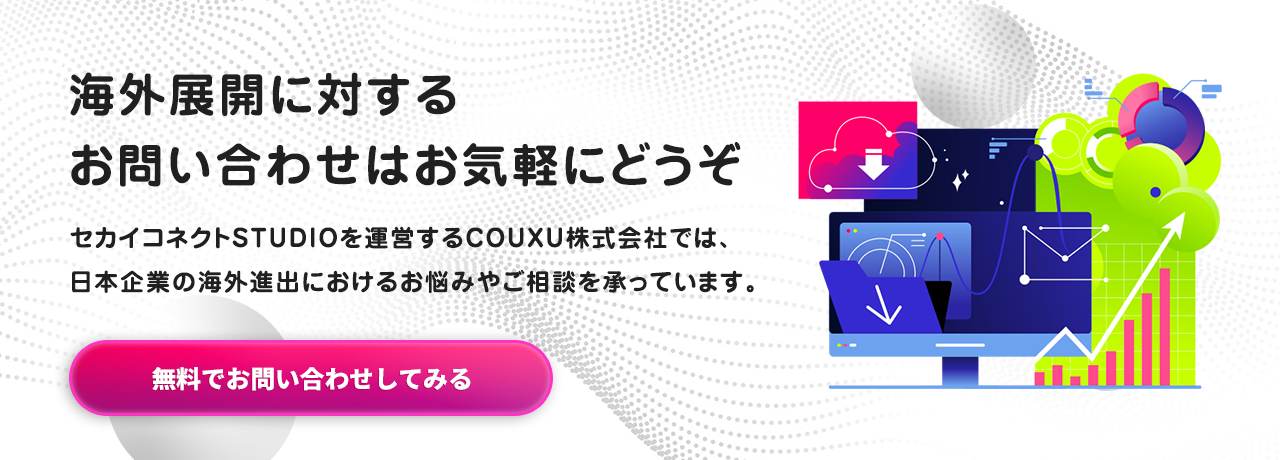輸出ビジネスに必要な原産地証明書 その意味と発行方法とは?
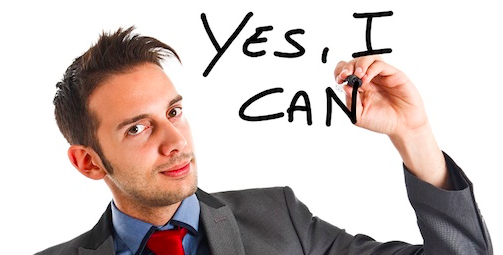
この記事は2024年3月8日に更新されました。
輸出ビジネスには多くの書類が必要になります。
「正直どれが何のためのものかわからない」「どうやって取得すれば良いの?」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、重要書類の一つである原産地証明書の意味や発行方法について簡単に解説していきます!
目次
原産地証明書とは
そもそも原産地証明書は、輸出入される貨物がどこで製造されどこから来たのかを証明する書類です。
近年では、A国で生産され、B国で製造され、C国に運ばれてきた、というような貨物も少なくはありません。
原産国を証明することで、適切な関税率を確定したり、その国で生まれたという本物である証拠として使われたりと、貿易において大きな役割を果たします。
原産地証明書には以下の二つの種類があります。
原産地証明書
日本各地の商工会議所で発行できる一般的な原産地証明書です。
輸入者が輸入国内で販売する際に原産地を証明したい場合や、輸入国の法律や契約書などで要求された場合などで必要になります。
特定原産地証明書
輸出国が経済連携協定(EPA)の提携国の場合に使われる原産地証明書です。
EPAに基づく原産資格を満たしているという証明となり、EPA税率が適用され、減税を受けられます。
原産地証明書取得までのステップ
まずは、前者の一般的な原産地証明書を取得するまでの流れを解説していきます。
貿易登録を行う
まず、各商工会議所で貿易登録を行います。この登録は、一つの商工会議所で一回のみです。異なる商工会議所に行った場合は、都度行います。
真実かつ正確な書類にて申請を行う旨を誓約するため、違反してしまうと全国の商工会議所で証明発行停止と登録抹消になってしまいます。
申請書類を作成・準備する
作成する主な書類は以下の3つです。
証明依頼書
商工会議所に備え付けられているので、書類の指示に従って記入して下さい。
ちなみにこの証明書にも、
・ゴム印によるラバー証明用
・署名による肉筆証明用
・外国産証明用
といった種類があります。
いずれにしても、
・貿易登録番号
・申請会社名
・担当者氏名
・担当者連絡先
・原産国コード
・仕向国コード
・品目コード
・証明件数
・証明料
の記入が必須です。
申請には手数料が発生すること、また代行業者が申請する場合は代行会社の項目も記入しなければならないこと、ご注意ください。
原産地証明書
発行者がフォーマットを基に自分で作成して申請します。
フォーマットは、各商工会議所のウェブサイトからダウンロード可能です。
この書類はすべて英語で記入するため、抵抗がある方、正確に作成できているか不安な方は、代理サービスを利用してみるのも一つの手段です。
コマーシャル・インボイス
貨物を輸出入する際に税関当局に提出した原本を商工会議所の控えとして提出します。コピーは不可です。
以下の名古屋商工会議所のページには記載例が掲載されていますので、参考にしてみてください。
インボイスの違いについて気になる方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
原産地証明書を申請する
各商工会議所の窓口へ行き、発給申請を行います。
申請時期としては、コマーシャル・インボイスの記載事項が全て確定してから船積み後6カ月以内が原則です。
6カ月以上1年以内になると別途典拠資料が必要となり、その期間以上になると発給不可となります。
原産地証明書を受け取る
書類に不備がなければ、午前に提出したら当日の午後に、午後に提出したら翌日の午前に受け取ることができます。
その際にも手数料がかかりますので、忘れないようにしましょう。
特定原産地証明書取得までのステップ
次に後者の特定原産地証明書を取得するまでの流れです。
必要事項を確認する
以下の4つのことを事前に確認します。
HSコード
品目ごとに定められている6桁の世界共通のコードのことです。
輸出したい商品のものを確認しましょう。
EPA税率の確認
先述した通り、輸出先の国がEPAの加盟国である場合、EPA税率が適応されます。
他にWTO税もあるため、EPA税率とどちらの方がお得に貿易できるのか確認してみましょう。
こちらはHSコードを基にJETROのデータベースから無料で調べられます。
各EPAの原産地規則
それぞれのEPAごとにどこまでを日本製とするのかルールが存在しているため、確認しましょう。
原産性
原産地規則も輸出相手国のEPAによって異なります。
輸出する製品が満たしているか否かを見ましょう。
企業登録を行う
全国のいずれかの商工会議所で行います。無料で登録でき、個人でも可能です。
有効期限は書類提出から二年間です。
原産品判定依頼を行う
企業登録が済むと、該当製品がEPAの提示している原産地規則を満たしているか、商工会議所が審査を行います。
ここで必要なのが、特定原産品である事を明らかにする資料です。
オンラインの特定原産地証明書発給システムを使ってアクセスして依頼します。3営業日で判定の結果が発表されます。
一度原産品と判断された商品は繰り返し発給申請が行えるため、判定依頼を何度も提出する必要はありません。
ただし、調達場所や価格が変化した場合は、再度判定依頼する必要があります。
特定原産地証明書の発給申請
審査の結果、原産品と判定された場合に発給申請が行えます。この手続きも先ほどのシステムで行うことができます。
原則2営業日で申請結果を受け取ることが可能です。
こちらも発給手数料がかかります。
まとめ
原産地証明書の意味や発行方法をおわかりいただけたでしょうか。
一般の原産地証明書は、手順をきちんと踏んでいれば迅速に発給できる書類です。
上手く活用してスマートに海外ビジネスを始めましょう!
原産地証明書に関連して、一体どこからどこまでが”Made in Japan”なのかをこちらの記事で詳しく解説しています。
気になる方はぜひご覧ください!