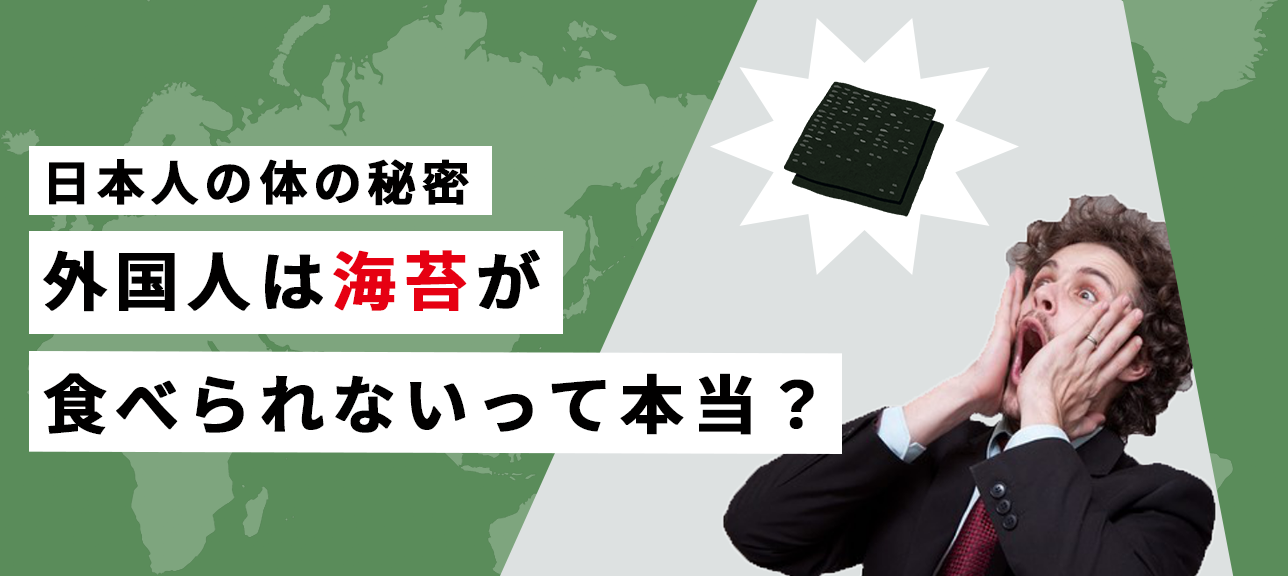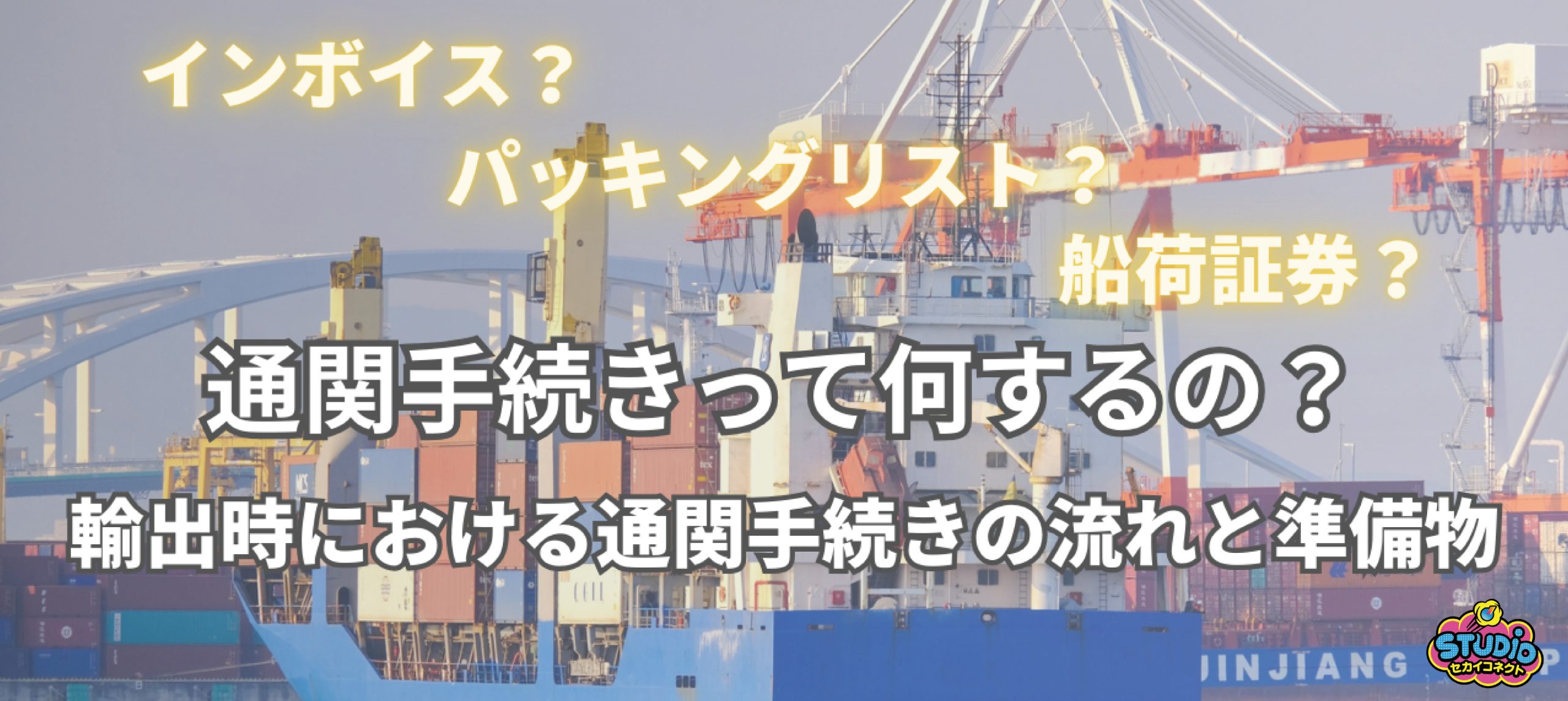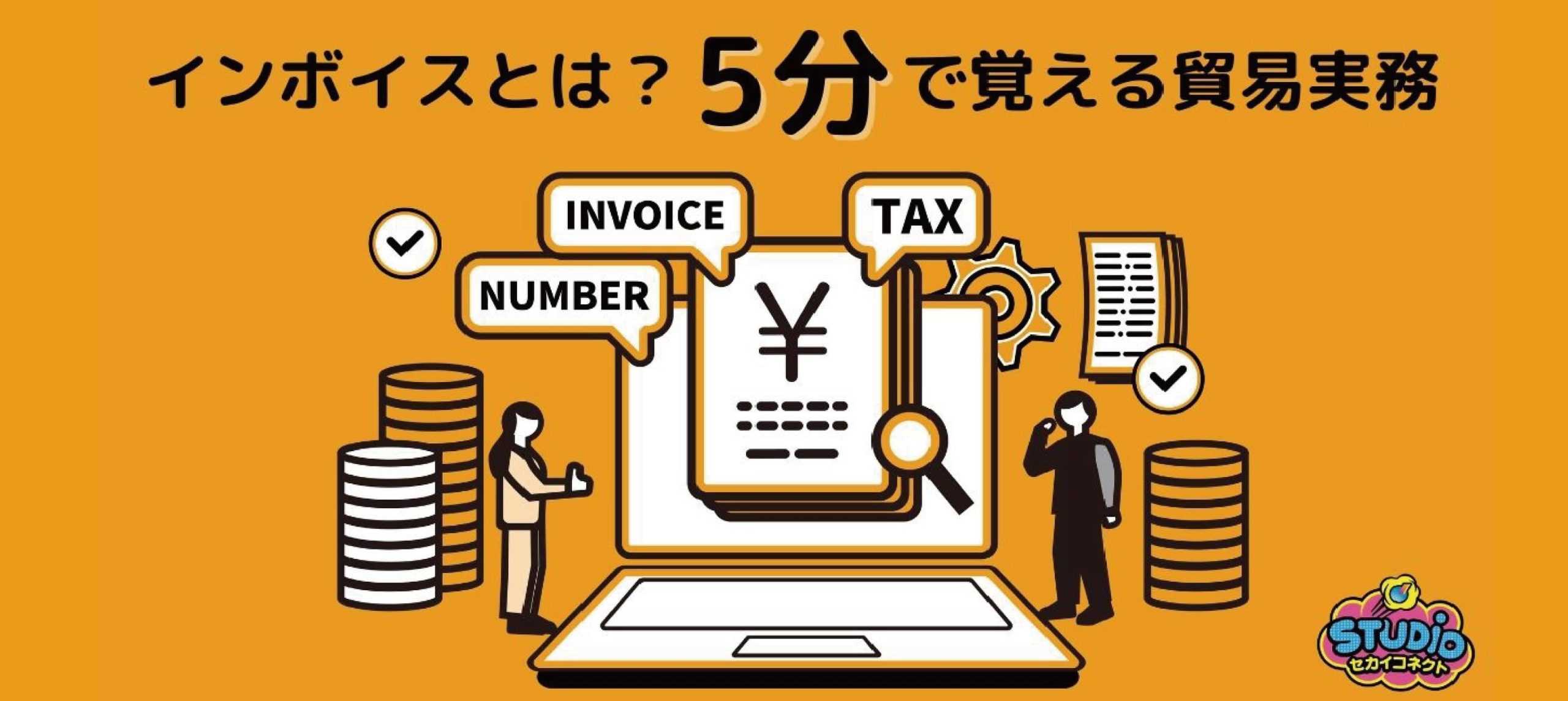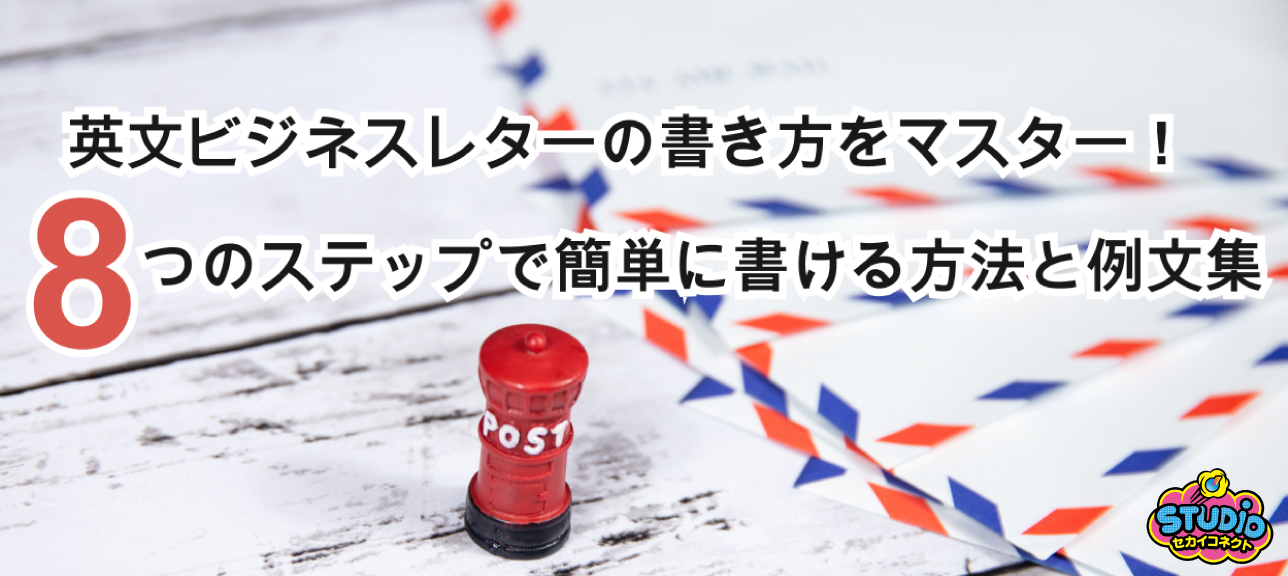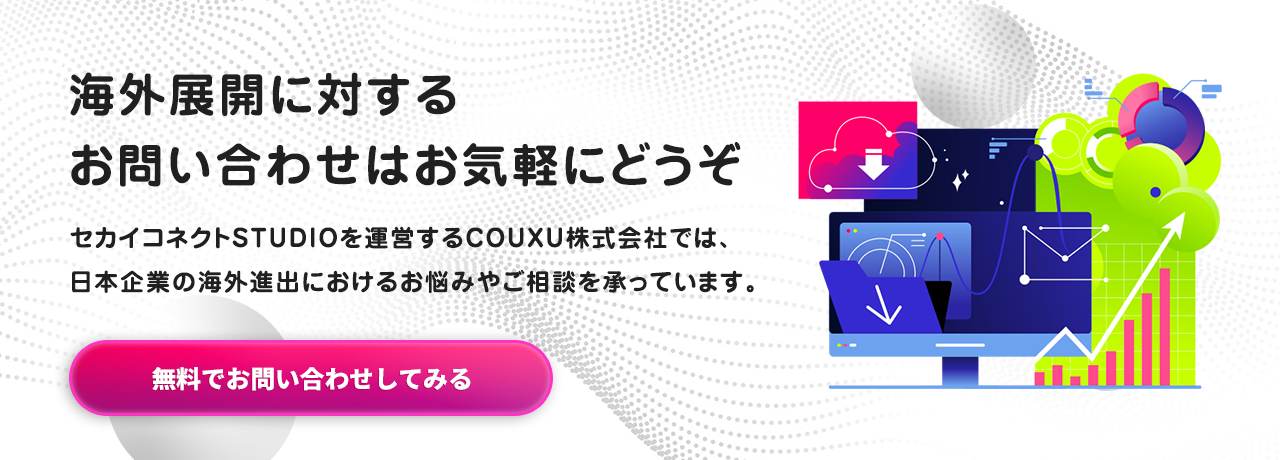消費量や人気の種類は?世界のお酒文化を比べてみた

大人の楽しみといえば、お酒!
日本には日本酒をはじめ、ビールやワイン、ウイスキーなど多くの美味しいお酒がありますよね。
今回は、海外にはどんなお酒の種類があるのか、どんな特徴があるのか、いくつかの地域に分けてお酒文化をまとめてみました!
お酒の消費量
世界のお酒について紹介する前に、一体どのくらいのお酒が飲まれているのか、その消費量のデータを見てみましょう。
2022年の経済協力開発機構(OECD)のデータによると、対象の48か国の一人当たりの年間消費量は以下のようなランキングになっていました。
1位 ラトビア
2位 リトアニア
3位 チェコ
4位 ブルガリア
5位 エストニア
…
38位 日本
…
上位9位まで独占しているのは北欧を中心としたヨーロッパの国々です。
アメリカやアフリカ、アジアといったその他の国々はそれ以下に位置しています。
日本も全体の中で38位と、かなり少ない方なんですね。
ヨーロッパのお酒文化
世界でもお酒の消費量が多いヨーロッパでは、主にビールやワインが好まれています。
ビール
こちらはKIRINの調査による2021年の国別一人当たりビール消費量のランキングです。
やはりヨーロッパの消費量が圧倒的で、1位のチェコと2位のオーストリアには2倍近くの差があります。日本の5倍強とは、想像もつかないですね。
なんとビールの価格が他の飲み物よりも安いということで、朝昼晩問わず飲む人も少なくはないようです。
ちなみに余談ですが、日本のビールのほとんどはこのチェコのピルスナーというスタイルなんだとか。チェコのお酒の味は日本人にも馴染みのある味だと言えます。
ワイン
ヨーロッパといえば、やはりワインですよね。
OIV(世界ブドウ・ワイン機構)の発表によると、2021年の国別一人当たりワイン消費量は、1位がポルトガル、2位はフランス、3位はイタリアという納得の順位でした。
しかし、実は最近はこうした国々でもワイン離れが進んでいるといいます。
特にフランスとイタリアは順位こそ保っているものの、消費量は徐々に減少しています。
食生活の変化によって、もっと気軽に飲めるようなビールなどの他のお酒が好まれる傾向になってきたのです。
様々なボーダーレス化が、長く続いてきた伝統や文化でさえも変えつつあるのかもしれません。
南米のお酒文化
日本ではまだあまり馴染みがないのですが、ブラジルなどの南米では現地さんのウイスキーやブランデーといった蒸留酒が人気です。
蒸留酒
実は南米で最も好まれている蒸留酒。
例えばブドウを原料としたペルーのピスコやボリビアのシンガニ、サトウキビを原料としたコロンビアのアグアルディエンテなどが有名な蒸留酒です。
日本で言うと芋焼酎のようなポジションなので、最初は飲みにくいことが多いそうです。
日本を含め世界にはまだまだ未進出の、南米の人々が愛してやまない蒸留酒のこれからに注目ですね。
東南アジアのお酒文化
一人当たりのお酒の消費量は上記二つには及びませんが、日本に近い東南アジアの国々でも密かに新しいお酒ブームが巻き起こっています。
ビール
ビールは年間を通して気温の高いタイやシンガポールで飲まれています。
特にタイでは、なんとビールに氷を入れて飲むといった習慣があるようです。
薄味が好きな国民性もあることと、ビールを保存する冷蔵庫の普及が襲置かったことなどがこの「ビールの水割り」が一般的な理由だと言われています。
日本酒
中でも中国で人気になってきているのが、我らが日本の日本酒です。
日本食レストランの増加や、訪日中国人の増加による日本酒の認知度の高まり、そして中国で一般的な白酒よりもほどよい度数でさっぱりとしている日本酒を好み始めた傾向が理由に挙げられます。
日本酒を含めた日本のお酒の海外進出については以下の記事でまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください!
世界のお酒はこんなにも違う!
国・地域によってお酒が飲まれている量や好まれている種類が大きく異なっていることをおわかりいただけたでしょうか。
しかし、人々の価値観や経済の動き、資源の変化によって、その傾向も必ずしも一定ではありません。
お酒を嗜む方々は、ぜひ世界のお酒の新しい傾向や文化の移り変わりに注目してみてください!
参考文献
・広島銀行, 「タイ人はアジアで1番ビールがお好き!」, https://www.hirogin.co.jp/lib/kaigai/bangkok/report/b2111/